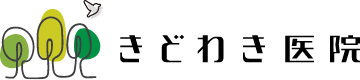その鼻の不調、年のせい?知っておきたい「年齢と鼻炎」の関係
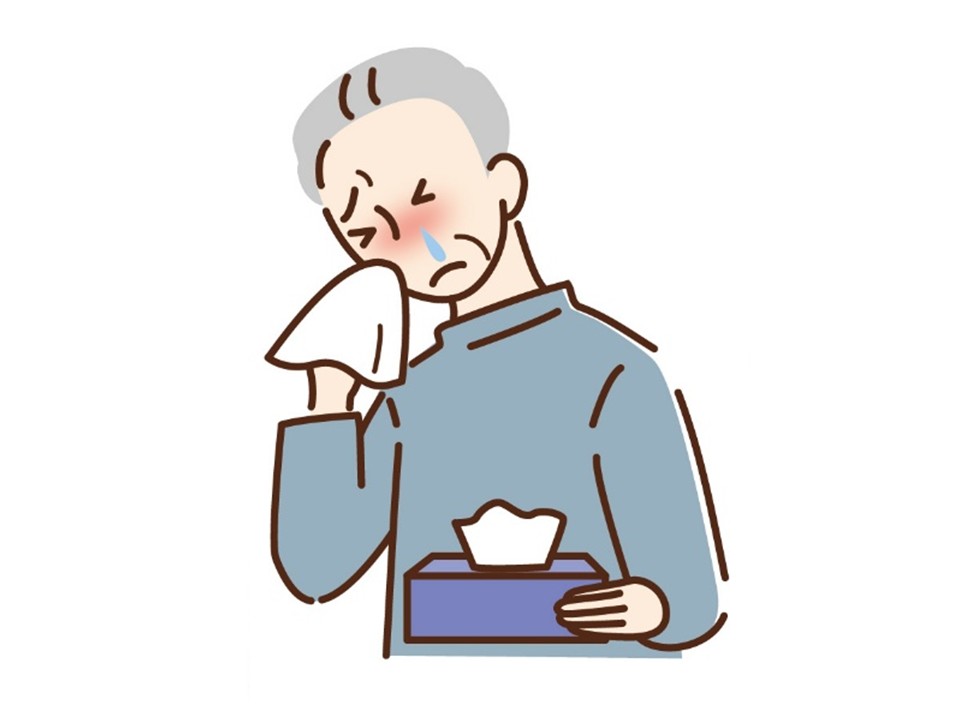
年齢とともに変化する鼻との付き合い方
こんにちは。滋賀県守山市、小児科・アレルギー科・耳鼻咽喉科のきどわき医院です。
加齢は鼻の機能や構造にさまざまな変化をもたらします。そのため、若い頃の鼻炎とは診断や治療の視点が異なってきます。特に急に寒くなるこの時期は、鼻水、くしゃみが出やすくなります。
今回は、年齢とともに変化する鼻炎の特徴と、治療のポイントについてお話しします。
年齢とともに鼻はどう変わる?
年齢を重ねるにつれて、鼻の機能や構造には変化が生じます 。
鼻の構造と粘膜の変化
鼻の軟骨などが弱くなることで、鼻の形が変わり、特に鼻の通り道が狭くなることがあります 。その結果、鼻づまりが起きやすくなります。また粘膜そのものが萎縮し、逆に鼻腔が広くなることもあります。
また鼻の粘膜にある、湿り気や温かさを保つための組織(鼻腺や細動脈)や、老廃物を外へ運ぶ線毛細胞の数も減ってしまいます 。線毛の数が減るため、鼻汁をのどに送る能力(線毛移送能)が低下します。
鼻の機能の変化とその結果
これらの変化が、「鼻の機能低下」につながります。
結果として、鼻汁がドロドロになったり、鼻の乾燥、喉に鼻汁が垂れる後鼻漏(こうびろう)、そして鼻の中にかさぶたができやすくなったりします。
一方で、高齢者の鼻粘膜は刺激に対する反応が過敏になり、普段は乾燥していても、ちょっとした刺激で鼻水が止まらなくなる、というコントロールが難しい症状が出ることもあります。
年齢を重ねると生じやすい鼻炎
加齢による鼻の変化が影響し、特に高齢者の方に生じやすい鼻炎には以下のようなものがあります 。
- 本態性鼻炎(血管運動性鼻炎)
アレルギーではないのに鼻炎症状があるタイプで、非アレルギー性鼻炎の中では最も多い疾患です 。
寒冷、タバコ、乾燥といった物理的・化学的刺激に鼻が過剰に反応してしまうのが特徴です 。
症状としては、くしゃみや鼻水が多く見られます 。
- 萎縮性鼻炎
加齢により鼻粘膜が萎縮し、血流や鼻腺の機能が低下することで、鼻腔が拡大し、乾燥した状態になってしまう病態です。
症状は、かさぶた(痂皮)の付着、異臭、鼻腔が広いのに感じる不思議な鼻づまり、そして粘っこい鼻汁が続く後鼻漏などがあります。
治療が難しく、鼻腔の加湿を促す鼻洗浄やワセリンの塗布といった保存的な治療が推奨されています 。
- 老人性鼻漏
鼻炎というよりも、年齢を重ねた方特有の症状の一つです。
持続的にサラサラした鼻水が鼻の穴(前鼻孔)から出てくるのが特徴で、朝方に多いと言われています 。
粘膜の温度低下で吐く息に含まれる水分が減少したり、線毛機能の障害で鼻汁が喉へ運ばれずに溜まってしまうことが原因と考えられています 。
治療としては、鼻や体を温めること(スチームで鼻腔内を温める、手足を保温するなど)が症状緩和に有効です 。また、冷えに効く漢方薬も有効性が示唆されています。
治療で特に大切なこと
複数の病態が絡み合っていることが多い
年齢を重ねた方の鼻炎は、上記の疾患がさまざまに合併し、病態を形成しているのが特徴です 。
例えば、萎縮性鼻炎とアレルギー性鼻炎が合併している場合、治療法は全く異なります 。個々の患者さんの病態に合わせた治療を行うことが大切です 。
薬の副作用への配慮
特に持病が多い方は複数の薬を内服している方が多く、体の機能も低下しているため、薬の選択に慎重さが必要です 。
鼻水の治療によく使われる抗ヒスタミン剤の中には、眠気の副作用が出やすいものがあり、それが原因で転倒のリスクが高まる恐れがあります 。そのため当院では、可能な限り眠気の副作用が少ない薬剤を選ぶよう心がけています 。
「症状緩和」を目指す生活習慣の工夫が大切です
このように、高齢者の鼻炎は複雑で、治療がなかなか難しく、安易な治療選択は転倒や萎縮性鼻炎の原因となるリスクを伴います。そのため、根本的な解決よりも、「症状を和らげる」ことに焦点を当てた日常生活の工夫が非常に重要になってきます。
鼻腔の保湿と洗浄

鼻の乾燥や粘度の高い鼻汁による不快感には、鼻腔洗浄で鼻の通りを良くしたり、ワセリンの塗布で粘膜の加湿を促したりする方法が推奨されています 。当院では診察時に温かい生理食塩水による鼻腔洗浄を行っています。
鼻と体を温める

サラサラした鼻水が出る老人性鼻漏では、粘膜温度の低下が原因の一つであるため、鼻をスチームで温めたり、手足を保温したりすることが症状緩和に役立ちます 。足湯も効果的であると言われています。
年齢とともに鼻の症状は変化しますが、その変化を理解し、適切な治療と日々のセルフケアを組み合わせることで、不快な症状を和らげることが可能です。