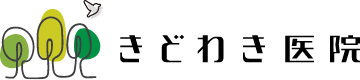インフルエンザワクチン「フルミスト」について
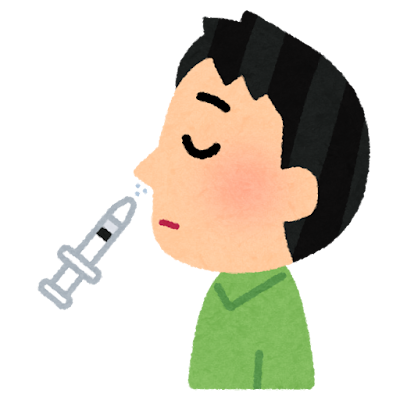
こんにちは。滋賀県守山市、小児科・アレルギー科・耳鼻咽喉科のきどわき医院です。
当院耳鼻咽喉科では昨シーズンから フルミスト®(経鼻弱毒生インフルエンザワクチン、LAIV) を導入しており、多くのお子さまに接種してまいりました。今回は保護者の皆さまに向けて、フルミストの特徴・効果・安全性をわかりやすく解説します。
フルミストとは?
フルミストは 注射ではなく、鼻へのスプレー で投与するワクチンです。左右の鼻腔にそれぞれ 0.1 mL、合計 0.2 mL を噴霧します。
含まれるウイルスは 弱毒化されたウイルス で、鼻・のどの粘膜で免疫応答を誘導します。
注射が苦手なお子さまにも受けやすく、接種ストレスを軽減できるという利点があります。13歳未満の方は注射のワクチンでは2回接種が必要となるのに対し、フルミストの接種回数は1回で済みますので、その点でもメリットがあると言えます。
効果(有効性)について
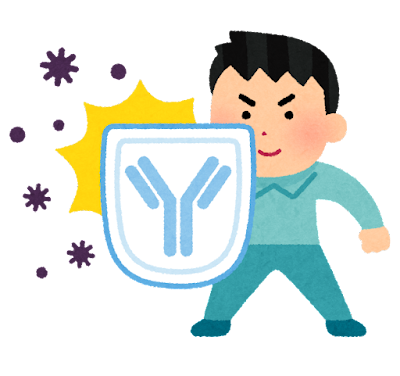
小児を対象とした日本国内試験では、プラセボ群と比較して 全株を合わせた発症予防効果 が一定程度認められました。
特に、ワクチン株と流行株がよく一致した場合(いわゆるワクチン株の予想が当たった場合)には予防効果が高くなるという傾向があります。
また、米国などの市販後調査データで、フルミスト と従来の注射のワクチンとの効果に明確な差はなく、フルミストも注射のワクチンと同等の効果があったとされています。
安全性・注意点
妊婦がいるご家庭の場合
妊婦自身にはフルミストを接種できません。しかし、同居するご家族がフルミストを接種すること自体は安全とされています。つまり、妊婦さんが同居しておられるご家庭内で接種されても問題ないということです。
新生児・乳児・高齢者がいるご家庭の場合
新生児・乳児(ワクチン接種対象外年齢)や高齢者がいる家庭でも、通常は問題ないと考えられています。
ただし、免疫不全状態 の方がいる場合(例えば重い基礎疾患、免疫抑制療法中など)は、慎重な判断が求められます。事前に医師と相談をお願いいたします。
接種できない方
- 2 歳未満の乳児
- 19 歳以上
- 妊娠中の方
- 免疫不全・免疫抑制中の方
接種可能か慎重な判断を要する方
- 重症喘息の既往
- ゼラチンアレルギー、卵アレルギーの方
- 過去にけいれんの既往のある方
主な副反応とその頻度
フルミストの副反応は、国内の試験でも報告されています。多くは軽くて自然に治まるものです。ご家庭で気をつけて見ていただきたい症状を、出やすい順にご紹介します。
- よく見られる(10%以上)
鼻づまり・鼻水、咳、のどの痛みなど。かぜのような症状が中心です。 - ときどき見られる(1〜10%未満)
のどの炎症(鼻咽頭炎)、食欲が落ちる、お腹の不調(下痢や腹痛)、発熱、体がだるい、筋肉の痛みなど。いずれも軽く済むことが多いです。 - あまり見られない(1%未満)
発疹、鼻血、胃腸炎、中耳炎など。 - まれに報告されているもの
顔のむくみ、じんましん、または持病(例:ミトコンドリア脳筋症など)の悪化など
また、接種後に「インフルエンザのような症状」が出ることがあります。ただしこれは、ワクチンに含まれる弱いウイルスの影響なのか、ちょうどその時期に流行している本物のインフルエンザにかかったのかを区別するのは難しいとされています。
ワクチンウイルスの排出と伝播
接種後、接種者の鼻やのどの分泌物から 最長 3〜4 週間程度、弱毒ウイルスが排出される可能性 が報告されています。
健康な方との接触はほとんど問題がないとされていますが、免疫が著しく低下している方とは接種後しばらく距離を取るようにしましょう。
接種されるご本人が授乳中の方は、乳児との近接接触を控え、手指衛生を徹底するようにしましょう。
抗インフルエンザ薬を使った後、フルミストを受けられるまでの目安
フルミストを摂取する前にインフルエンザにかかってしまい、抗インフルエンザ薬を使用した際についてご説明します。
まず、インフルエンザにかかったのにフルミストを打つべきかどうかですが、フルミストは複数のウイルス株を含んでいるので、同シーズンに別のウイルス株に感染する可能性を考えると、接種が望ましいと考えられます。
また、抗インフルエンザ薬を使った直後だと、薬がまだ体に残っていてワクチンの効果が下がる可能性があります。
短く効く薬(タミフル、リレンザ)は2日(48時間)、長く効く薬(イナビル、ゾフルーザ)は2週間、フルミストの接種までに間をあける必要があります。
まとめ
フルミストは、注射が苦手なお子さまにも受けやすい経鼻型ワクチンで、昨年の当院での経験では、最初は怖がっていたお子さんも接種後は「あれ、もう終わったの?」という反応の方が多く、痛みが全くないことに喜んでおられる方が多い印象でした。
新生児や高齢のご家族、また妊婦さんがいらっしゃるご家庭でも、安心してお受けいただけると考えられています。ご心配な点があればどうぞ遠慮なくご相談ください。